|
キリモミ君の冒険 その51
|
|
交通安全教室
|
|
校庭に石灰で描かれた横断歩道。焼けた砂の匂い。昼下がりの陽光の中で、彼女は軽い目まいを覚えた。小学生の頃、全校朝礼でよく貧血を起こして倒れた記憶がよみがえってきたのだ。だが、今の彼女は警官なのである。そんな過去の記憶を振り払うように短く笛を吹いた。マニュアルどおり、交通安全教室は順調に進んでいた。毎年繰り返されるこの行事に、児童達もマニュアルどおりの対応をしていたからである。 一方、キリモミ君は車での移動中に、トランクの中ですでに目を覚ましていた。しかし交通安全教室における腹話術人形と婦人警官の『お姉さん』との掛け合いは最後の人気プログラムだったため、キリモミ君の出番までは、まだしばらく外に出ることが出来なかった。そのうち暇になってきたキリモミ君は窮屈な空間の中でどうにかポケットの中の錐を取り出すことに成功し、トランクの内側から小さな穴を開け、その穴から校庭で繰り広げられている交通安全教室の様子を興味深く観察していたのだった。 そして、マニュアルどおり交通安全教室は最後のプログラムを迎え、キリモミ君の入ったトランクはステージがわりに用意された朝礼台の上に運ばれた。最後の大舞台に婦人警官の『お姉さん』は大きく深呼吸をして朝礼台に上がり、トランクの留め金に手をかけると、気合いを入れて笑顔を作って大きな声を出した。 「さあ! みんな! 今日ここで勉強したことを、ケンちゃんと一緒に復習してみようね! それじゃ、みんな、いいかな?! 大きな声でケンちゃんを呼んでみよう! せーのっ! ヶ〜ンちゃ〜ん!」 お姉さんの掛け声と一緒に児童達もマニュアルどおりに声を合わせた。 「ヶ〜ンちゃ〜ん!」 すると、トランクの中からいつもの見慣れた「ケンちゃん」とは何となく違うボロ服を身にまとった汚い腹話術人形が飛び出しながら叫んだのだ。 「ヶ〜ンちゃ〜ん!」 いつもと違った展開に子供達は一瞬、どう対応していいのか分からず、お互いの目を見合わせた。が、もっと面食らったのは他でもなく「お姉さん」だったのである。だが、彼女は次の一言で事態をすっかり建て直しにかかったのだ。 「ちょっと! ケンちゃん! なにとぼけたこと言ってるの? あなたがケンちゃんでしょ?」 だが、このツッコミに、なんとキリモミ君はさらなるボケで応戦し始めたのである。 「僕? 僕はケンちゃんじゃないさ、僕は生まれたときから、ずっとキリモミ君だよ。ケンちゃんはどこ? お〜い、ヶ〜ンちゃ〜ん!」 生徒達はこの展開に大笑いだった。しかしマニュアル通りの人生を送ってきた彼女にとって、この事態はとてつもない一大事だったのだ。すっかり上気した顔の彼女は、とにかくマニュアル通りの流れに軌道修正しようと躍起になっていた。 「じゃあいいわ、キリモミ君でも。ところでキリモミ君、今日、ここで勉強したことを復習してみようね。道路を渡るときはどうするんだっけ? まず、かならず横断歩道を渡るんだよね。その時はどうするの?」 キリモミ君は目を白黒させながら言った。 「横断歩道を渡ったからって、安全とは限らないよ。」 お姉さんの顔は真っ赤だった。キリモミ君は続けた。 「正解は横断歩道で手を上げて、右見て左見て、さらに右見て車が来なければ渡るっていうことなんだろうけど、僕に言わせれば、車が来ないんだったら、手を上げる必要はないし、さらに横断歩道だろうがそうでないところだろうが、車が来ないと判断して渡ればそれでいいと思うんだ。それに僕の経験上では、横断歩道で手を上げても停まってくれない車は沢山いるね。」 子供たちはうんうんと頷いていた。ポケットの中のチューは苦手な子供が沢山いる学校に再び来たということで、今まではボロ服のポケットの底にじっとしていたものの、この展開に危機を感じていた。さらにキリモミ君は続けた。 「つまりはみんなだって『交通安全教室』なんてものが何の役にも立たないことを知っているんだよ。本当の意味で交通事故を減らす鍵を握っているのは車を運転している大人たちなんだからね。ここで教えていることってのは、いかに事故に遭わないようにするか、あるいはどうすれば走る車の邪魔にならないか、ということだけなんでしょ? だけど、やっぱりおかしいよ。夜歩く時には反射材を付けて車からよく見えるようにしよう、なんて。本来なら、車を運転する大人がいつもよりさらに歩行者に気をつければいいことなのに。どうしていつも歩行者は車のスムーズな流れを乱さないように気を遣わなくちゃいけないのかな? 車は広々とした車道を偉そうに走っていて、歩行者はビクビクしながら狭いドブ板の上を歩かされているんだ。雨の日には泥水をかけられながらね。おかしいよ。本当に交通安全に対する教育が必要なのは横柄な顔をして車を運転している大人の方なのに、どうして大人に対する交通安全教室は開かれないのかな?」 婦人警官の「お姉さん」の顔はこれ以上ないくらいに真っ赤だった。ポケットの中のチューはまずいと思っていた。そして、今度はどこのゴミバケツに放り込まれるのか、と辺りを見回した丁度その時、頂点に達した彼女のとった行動は思いもかけぬ方向に展開していったのである。ふっ切れた様子の彼女はポツリと言った。 「その通りだわ、キリモミ君。まさにその通り。私も前から心の底ではそう思っていたのよ。」 拍手が沸き起こった。子供たちが笑顔で心から手を叩いていた。周りにいた教師達は最初この様子に戸惑っていたものの、やがて、一人、二人と拍手を始め、あっという間に校庭全体が大きな拍手に包まれた。 そして、まだこの段階では誰も気がついていなかったが、これまでどんなことがあっても乱れることのなかった『大いなる機械』の歯車の回転が、このとき僅かに狂い始めていたのである。 |
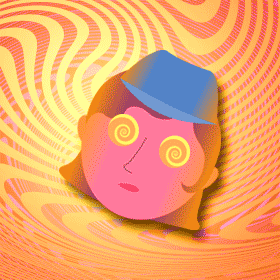 |
